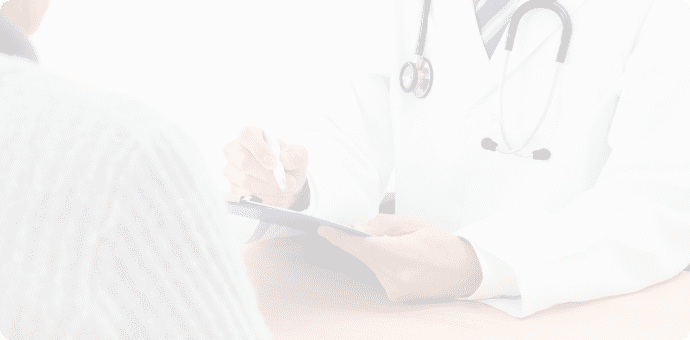長時間労働者に産業医面談を実施する基準や流れとは?面談のポイントも解説
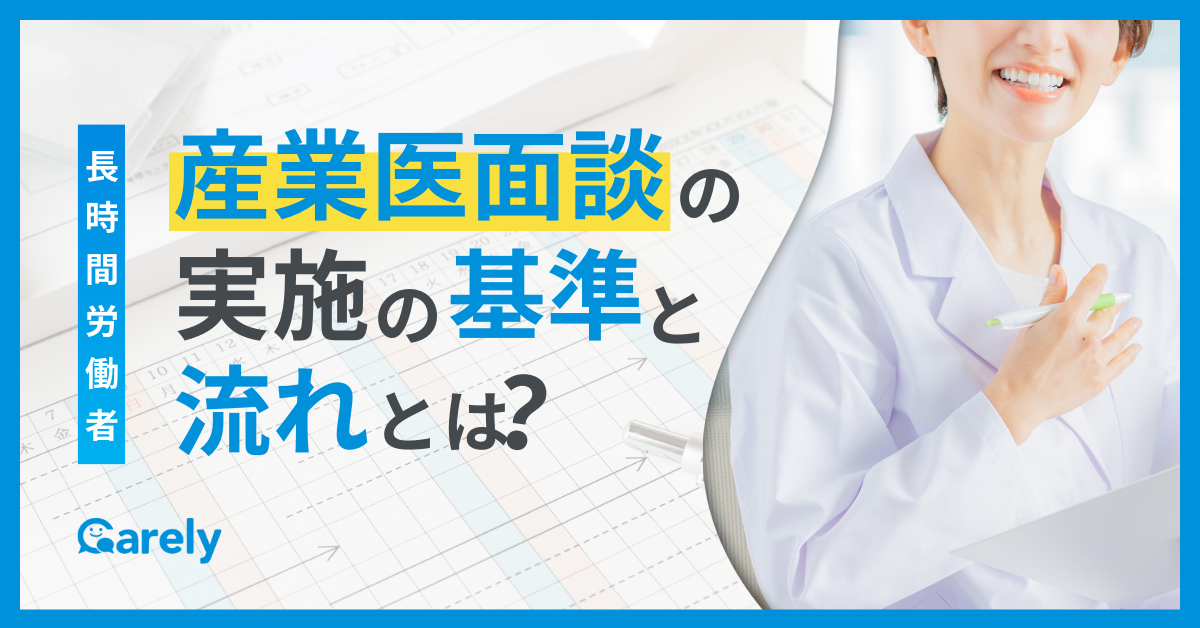
本記事では、長時間労働者に対する産業医面談、いわゆる面接指導制度について紹介します。長時間労働の対策は国をあげて実施されており、2019年の働き方改革関連法案により、面接指導制度も実施基準が強化されています。
健康経営を行う上でも、様々な心身の不調の原因となる長時間労働対策は重要な取り組みとなっています。中でも産業医面談は不調者の早期発見・対処のために必要不可欠です。
法改正後の基準や流れを押さえて、適切な長時間労働者への面接指導を実施しましょう。
目次
長時間労働者への産業医による面接指導制度とは?

長時間労働者への産業医による面接指導制度とは、長時間労働者の勤務実態や疲労蓄積度を把握した上で、産業医が行う面接指導のことです。労働安全衛生法(第66条の8第1項)で義務づけられており、企業は長時間労働者に対して産業医面談を実施しなければなりません。
労働安全衛生法では面接指導について、以下のように定義されています。
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされています。
引用:長時間労働者への 医師による面接指導制度について
以前からこの制度は存在していましたが、2019年の働き方改革関連法により、その対象が拡大されました。では、面接指導の対象となる長時間労働者の基準とはどのようなものなのでしょうか。
産業医面談が必要になる長時間労働者の基準
法改正後の産業医による長時間労働者への面接指導の対象となる長時間労働者は、下の図のとおり、働き方によって3つの区分に分けられます。

画像引用:労災疾病臨床研究事業費補助金研究「医師による長時間労働面接指導実施マニュアル」
法改正前は1ヶ月あたり100時間を超える時間外・休日労働をした労働者に対し、疲労の蓄積が認められる場合、医師による面接指導をすることが義務付けられていました。
法改正後は、図のように時間外・休日労働が「月100時間超え」から、「月80時間超え」に基準が変更になった他、新たに高度プロフェッショナル制度が創設され、制度利用者向けの基準も新たに設定されています。
また、努力義務として事業者が自主的に定めた基準に該当するものに対しても産業医面談を行う必要があります。
この法改正を機に、多くの企業では実施基準となる80時間の前段階で独自基準を設定するようになりました。
長時間労働の産業医面談基準は、一般的に二段階で設定されます。時間数は会社によって異なるのですが、一例をご紹介しましょう。
| 月の残業時間 (総労働時間 – 法定労働時間) | 面談のルール |
|---|---|
| 30時間/月 | 部門長または労務との面談を実施または疲労蓄積度チェックリストを実施 |
| 60時間/月 | 本人の申込に関係なく、産業医面談を実施 |
働き方改革関連法とは

働き方改革関連法とは、2019年4月1日から施行されている労働基準法をはじめとした、働き方改革を目的とした労働関連法の法改正を進めるための法律のことです。
この法案では、ワークライフバランス実現のための長時間労働抑制や、非正規雇用労働者の保護、多様で柔軟な働き方の実現などを目的としており、先述したように長時間労働者に対する産業医面談の基準強化も含まれています。
法案提出時の理由としては、下記のように定められています。
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため、 時間外労働の限度時間の設定、高度な専門的知識等を要する業務に就き、かつ、一定額以上の年収を有する労働者に適用される労働時間制度の創設、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者と通常の労働者との間の不合理な待遇の相違の禁止、国による労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針の策定等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
引用:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 理由
働き方改革関連法による主な改正内容については以下になります。
- 1時間外労働の上限規制を導入
- 産業医・産業保健機能の強化
- 年次有給休暇の確実な取得
- 中小企業の月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ
- 正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
- 「フレックスタイム制」の拡充
- 「高度プロフェッショナル制度」を創設
- 勤務間インターバル制度の導入促進
詳しい内容については以下の記事にてご紹介しておりますので、ご参照ください。
記事:過重労働の基準知ってますか?会社が義務違反にならないための対策
長時間労働者への産業医面談の流れ
長時間労働者に対する産業医面談は法改正に伴い、関わる業務も厳格に規定されるようになりました。単に対象者に対して産業医面談を実施すればよいだけではなく、従業員の労働時間を把握し、労働者の情報を提供、本人の申し出をもとに産業医面談を実施しなければなりません。また、面談後の事後措置についても規定されています。

以下では、事前対応から、面談、事後措置まで、産業医面談の一連の流れを、新たに追加となった規定内容とともに紹介していきます。
長時間労働者に係る情報の産業医への提供
2019年4月の労働安全衛生法の改正により、産業医が面接指導を実施する際に、企業は対象の従業員の労働状況を提供することが義務化されました。
そのため、企業は従業員の勤務状況について適切に記録を取る必要があります。
厚生労働省令に定められている記録方法としては、タイムカード、PCなどの電子計算機の使用時間の記録、その他適切な方法での記録が義務付けられています。
適切な面接指導を行うためにも、従業員の勤務状況をしっかりと把握し、産業医と情報共有を行いましょう。
また、対象の従業員の健康状態を把握する上で必要な情報や資料も提供しなければなりません。健診結果やストレスチェック結果、疲労蓄積度チェックの結果など必要な情報をまとめておきましょう。
労働時間に関する情報の通知
産業医に労働状況を共有するとともに、対象となる従業員本人に、産業医面談が必要になる基準の法定外労働時間を超えたことを通知しなければなりません(労働安全規則第52条の2第3項)。
この通知は従業員本人に産業医面談の必要性があることを理解してもらい、産業医面談の申し出を勧奨するために必要な措置となります。
情報を通知する際は、合わせて実施方法や時期などの案内も行うとよいでしょう。
産業医による申出の勧奨
企業からの面談勧奨と合わせて、産業医は共有された情報を元に、対象の従業員に面談の勧奨を行うことができます(労働安全衛生規則第52条の3)。
申出・面談
対象となる従業員が面談を申し出たら、産業医面談を速やかに実施します。
企業が面談が必要な従業員が申し出を行いやすいように、環境や体制を整えることが重要です。申し出のルールについては、東京都労働相談センターが以下のような例を上げています。
- 過重労働者全員に「疲労蓄積度チェック」を実施させ、該当する労働者全員を申出があったものとみなし、自動的に面接対象者とする
- 過重労働者全員に電子メールで、毎月産業医面接を受けるように告知する
- 過重労働者で、かつ、面接を受けていない人のリストを作成し、未受診者がいなくなるよう、定期的に通知を送る
- 時間外労働の申請をする際に、時間外労働時間の累計によってアラートが出るように設定する
参考:東京都労働相談センター
疲労蓄積度チェックは、面接申し出の代わりにも利用できるものになっているため、活用することで産業医面談をスムーズに実施することができます。
疲労蓄積度の活用方法については、以下の記事もご参照ください。
記事:過重労働者の産業医面談で、疲労蓄積度チェックリストを有効活用する方法
医師の意見聴取・事後措置の実施
産業医面談の内容をヒアリングした結果を元に、長時間労働の対策を実施します。
▼長時間労働の対策例
- ・就業場所の変更
- ・労働時間の短縮
- ・所属部署の転換
- ・業務内容の見直し など
人事担当者が勝手に判断するのではなく、産業医の意見を聞いた上で適切な対策が必要です。
また、メンタルヘルスの不調が見られる場合は、精神科医などと連携した対応が求められます。たとえば、うつによる過労自殺を防ぐための継続的なケアや、気軽に相談できる窓口の設置などの取り組みが有効です。
事後措置の内容を産業医に報告
企業は事後措置を実施したあと、その措置内容を産業医に報告しなければなりません。
また、産業医は措置内容が対象となる従業員の健康維持を図るために不十分だと判断した場合は、企業に対して勧告を行うことができます。
ただし、勧告内容については、事前に企業から意見を求めなければいけません(労働安全衛生法第13条の5、14条の3)。
衛生委員会等への報告
企業は事後措置の措置内容について、産業医から勧告を受けた場合、勧告内容を衛生委員会に報告しなければなりません。
勧告の内容、勧告を受けて行った措置、今後行う措置などについて報告します。また、措置を取らなかった場合もその理由を報告しなくてはなりません。
衛生委員会で議題に上げることで、職場での健康被害の拡大を防止し、企業として長時間労働の対策を行っていくことが必要です。
長時間労働者への産業医面談で注意するべきポイント

ここまで長時間労働者への産業医面談の意義や実施の流れについてご紹介してきました。産業医面談は長時間労働による心身の不調を早期発見・対処するためにも重要な取り組みだということがわかってきたと思います。
では、産業医面談をスムーズに実施するためには、どのような点に気をつければよいのでしょうか。以下では、産業面談を実施する上で注意するべきポイントを、3つ、ご紹介します。
産業医面談を拒否した場合の対応
産業医面談の対象になっているにもかかわらず、従業員自身が面談拒否をすることもあります。
その場合は、企業側から産業医面談を強制することはできません。従業員本人から面談希望の申し出があった上で、実施するようにしましょう。
ただしすでに長時間労働をしている状態のため、健康障害のリスクが高まっている可能性もあります。面談を拒否されたからと言って、そのままにするのではなく、法律によって義務付けられていることを伝えた上で受けたくない理由を聞いたり、産業医面談で得られるメリットを伝えたりすることも大切です。
産業医面談に関わるプライバシー
産業医面談を拒否する理由として、「同僚・上司に知られたくない」「人事考課に影響するかも」という不安の声をよく耳にします。
しかし、産業医には労働安全衛生法 第105条により、面談で知り得た従業員の情報を他人に漏らしてはならない守秘義務が課せられています。
また、産業医面談は企業の義務であり、面談の内容を元に従業員の不利益になる扱いを行うことは許されません。
もちろん、健康管理上必要な情報は本人の同意の元で、報告を行いますが、同意のない報告は守秘義務違反となるため、心配する必要はないということをしっかりと伝えるようにしましょう。
オンライン環境への対応
長時間労働者に対する産業医面談の基準が強化されたことにより、より多くの従業員が産業医面談の対象となることが考えられます。あまりにも面談対象者が増えると、産業医の勤務時間だけでは対応するのが難しくなってきます。
そのため、ビデオ通話などを活用したオンライン面談を利用することも検討するとよいでしょう。オンライン面談を活用すれば、移動時間を短縮することができ、会議室を抑える必要もないため、対面の面談よりもコンパクトに実施することが可能です。
また、従業員側としても周りの目を気にしなくてもよい点や、時間の融通が効くなど、メリットも多く、面談をより受けやすくなります。
以前は面談について原則対面とされていましたが、2020年の11月にはオンラインによる面談も可能になる通達が厚生労働省から出ています。
オンライン面談をするための諸条件などもまとめられているため、詳しくは以下をご参照ください。
面談後のケアやフォロー体制
長時間労働者に対しては、産業医面談後もこまめなケアやフォロー体制が必要になってきます。
時間外労働が常態化している従業員の場合、産業医面談を行っても、再び時間外労働を繰り返す可能性が高いです。また、長時間労働が続いたことで、心身に影響が出ている場合、環境が変わっても体調や精神面の様子を注意深く見ていかなければなりません。
具体的には、ラインケアや1on1など、対象者と近い立場の人間によるフォロー体制の充実や、産業医からの助言を元に就業制限や労働時間の制限を設け、注意深く経過観察を行う方法があります。
健康管理システムなどで、すぐに所見や面談履歴を確認できるようにグルーピングしておくとよいでしょう。
自社と相性のいい産業医と連携して、長時間労働の解消を
長時間労働対策はいまでは法令遵守の観点だけでなく、従業員の健康を守るための二次予防の観点からも企業が取り組むべき課題となっています。
その中でも、産業医面談は従業員の不調を早期発見し、早期対処するための重要な施策です。新たな基準を把握し、しっかりと対策を取ることが望ましいでしょう。
産業医面談を含め、長時間労働対策をより有効な取り組みとしていくためには、自社にあった優秀な産業医との連携が必要不可欠です。
Carelyでは、現職の産業医である代表が監修する産業医の紹介サービスを実施しています。ただ、産業医を紹介するだけでなく、貴社の抱える問題や、規模感などを把握した上で、最適な産業医をご紹介いたします。
自社と相性のよい産業医をお探しの場合は、ぜひご相談ください。
資料ダウンロードはこちら
 についてもっと知りたい
についてもっと知りたい
お問い合わせ・
資料ダウンロードはこちら
Contact